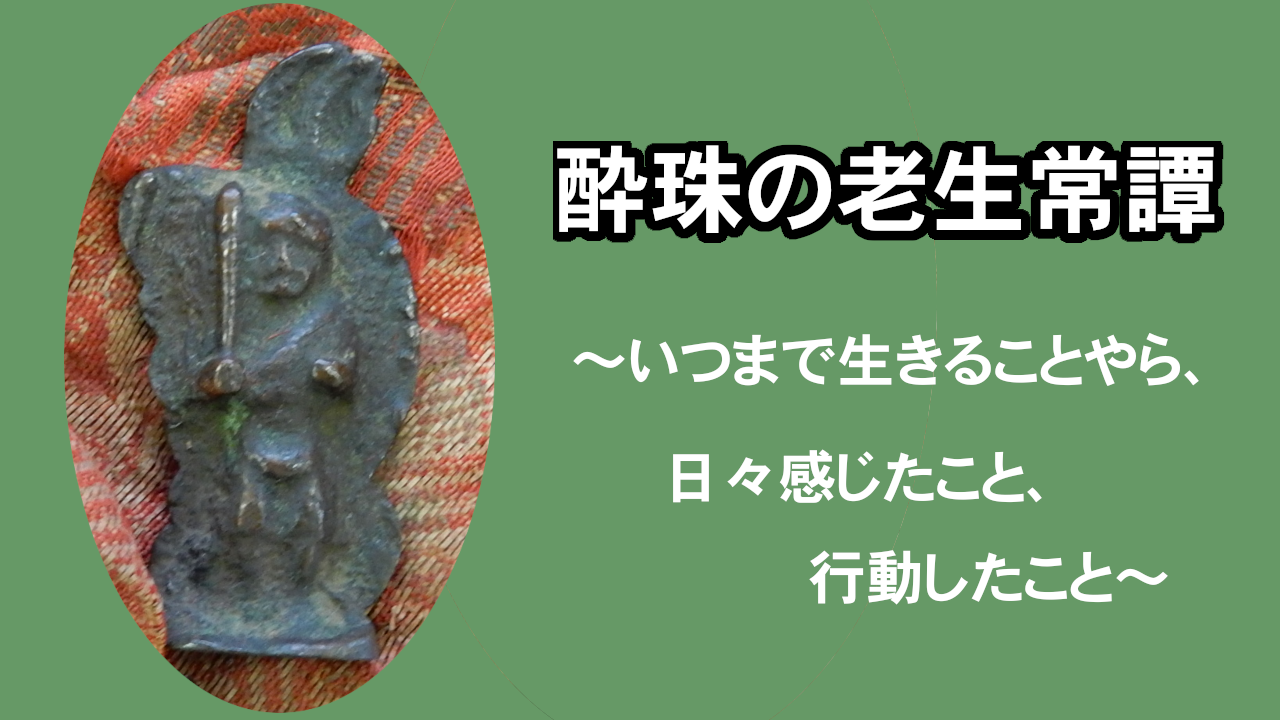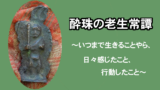元禄十三年(西紀一七〇〇年)の今日徳川光圀卿が歿した。本年もいよいよ歳暮に近づいたことは誰しも心付けど、我が寿命も追々最後の日に近づくことは更に思を寄せない。然るに、上下貧富の区別なく、一とさらひに掻き集めて行くものは死である。死の手が何時我れを浚(さら)ふともこれに応ずる心得は欲しい。光圀卿の歌に、
荒磯の岩にくだけて散る月を 一つになしてかへる波かな
いつの年いつの月日のその時か 遂に我が世の限りなるべき
一日一言(新渡戸稲造)
私の尊敬している教育者の一人である新渡戸稲造先生。
有名なのは著書『武士道』、国際連盟事務次長、東京女子大学初代学長という経歴はご存じのことと思われる。
また、今回のお札改定変更で同じ教育者の津田梅子氏へと交代したが日本銀行券の五千円券の肖像としても知られているはず。
この人が自分の助となつた格言を集めて、その日その日の教訓になる格言を日本人が理解できるように、また、簡単な文章で一日の精神的糧になるようにと書き残したのがこの文書である。ただ、1915年(大正4年)の脱稿なので、また、文語文の形態から令和のZ世代人は理解できるかなは甚だ疑問であるが…
もう一つの特徴としては一日分を声高らかに誦(しょう)しても一分以上を要しない短文であるということ。
あなたも私のブログを見ながら音読してみませんか?
今日の糧を得られるかもわかりませんよ。